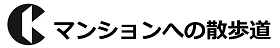マンションの仕組み(第四十九歩)
■花鳥風月 / マンションに係る建設業法の改正
建設業法の改正が2024年6月に公布されて、公共工事に順次施行され始めています。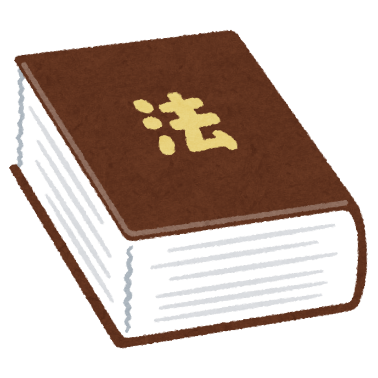
その目的は日本が世界に誇る建設技術の衰退防止です。建設業はインフラ整備や災害時の応急対策などを担う地域の守り手でもあるので、現在の建設業を取り巻く環境の改善が必要なのです。
建設業の就業者は年々減少しています。さらに高齢化も進んでいます。また、全産業の平均年収が約500万円なのに対して建設生産労働者は約430万円と低い水準です。加えて建設資材の高騰で建設業者の経営を圧迫しているため、建設生産労働者の賃金は上がりません。
建設業の年間出勤日数は全産業と比べて11日多いので、当然ですが労働時間も多くなります。
「働き方改革」で時間外労働の上限規制が導入されて改善が進んできていますが、それでも特に民間工事では週休2日の確保ができていないのが現状です。
私も130億円のマンションを建設していた時、ピーク時では1か月で2日しか家に帰れませんでした。
今回の法改正は公共工事となっていますが、これは国がまずは自分の公共工事から始めますと言うアナウンスなので、徐々に民間工事にも浸透していきます。マンションの管理組合は建設工事の発注者の立場になるので、マンションの修繕工事にポイントを絞り、将来の注意事項を簡単に説明します。
まず、契約書が変わります。資材高騰に伴う請負代金等の「変更方法」が契約書への法定記載事項となります。これからは公共工事で使用される契約書が民間工事でも利用され始めることになります。
次に受注者(建設工事会社)は資材高騰等の「おそれ情報」を注文者に事前に通知することが義務になります。「おそれ情報」の具体的内容は、天災などの自然的又は人為的な事象により生じる、資機材の供給不足や遅延・価格の高騰、労務の供給不足又は価格の高騰です。
受注者は客観性を有する資料等を根拠に発注者に対して見積書提出等で通知します。この場合、発注者は誠実に協議に応じなければなりません。正当な理由なく協議を拒絶したり、遅延させたり、打ち切ることは建設業法違反となります。これは公共工事に適用され、民間工事では努力義務になりますが、請負代金等の「変更方法」が記載された新しい契約書の場合は注意が必要です。
また、「おそれ情報」の事前通知が無かったことのみでは協議を拒む理由にはなりません。最初に記載しましたが建設業法が改正されたのです。発注者は誠実に協議に応じる必要があります。
「おそれ情報」は発注者から受注予定者にも通知が必要になります。例えば、地盤沈下が発生するおそれがある場合や、発注者しか知らない埋設物や文化財などがある場合は通知しなければなりません。
もう一つ発注者に求められる対応として、「不当に低い請負代金の禁止」があります。
一般的なマンション管理組合には難しい内容ですが、適正な工事金額を把握するのには良い機会と考えて、日ごろから積極的に情報収集に努めると、受注者からの見積書を見る目が変わって行きます。
大きな本屋さんには建設資材や労働単価に関する厚い書籍が3種類ほど約5,000円で売っていますので、管理組合で購入して、提出された見積書と比較すると簡単に理解できます。
注意が必要なのは「長期修繕計画を基に修繕積立金を決めているのだからこの金額以上は出せない」との発言はその後の協議に慎重さが求められます。受注者が資材の製造を行っていたり、多くの在庫を持っていれば低い請負代金は認められますが、根拠もなく「この金額でお願いします」も注意が必要です。
今後は建設Gメンによる請負契約に係る取引実態の調査が行われ、改善指導等が行われます。
そして、受注者は「働き方改革」の枠組みの中で工事工程表を提出しますので、認めざるを得ません。
次回は、マンションにおける工事の安全について説明します。
(建築積算士/マンション管理士 福森 宏明)